

(環境ビジュアルウェブマガジン「ジアス・ニュース」での連載より)
「ミナマタ」と聞いて思い浮かべるイメージは……? 公害による環境汚染、水俣病で苦しむ患者たち、長年の差別と偏見、それとも……?
山間地が市域の75%、源流から河口まで一つの水系で、山も森も川も海もある、日本の縮図のような熊本県水俣市。豊かな自然と農林水産業、そして工業も盛んな水俣市は、人口2万7500人、高齢化率約30%で、近代化による発展と衰退を経験している。
かつて公害で苦しんだ水俣市が、いま再び「ミナマタ」として注目を集めている。水俣病の負の歴史を乗り越え、プラスの資産に転じていく。日本で最も環境に配慮したまちとして、昨年日本初の「環境首都」に選ばれた。

水俣病資料館から不知火海を臨む。この美しい海はかつて公害で苦しんでいた
■水俣は、日本の近代を映し出す鏡である。
熊本県は最南部・鹿児島県との県境に位置する水俣市は、「ミナマタ」として世界に知られる。水俣病が公式発表されたのが1956年5月1日。認定患者数は2271人、うち死亡者が1746人(2011年7月末現在)、被害者は5万人ともそれ以上とも言われている。
水俣市は、日本の近代化における典型的な栄枯盛衰をたどってきた。水俣村時代の1908(明治41)年に日本窒素肥料株式会社(通称チッソ:現JNC)を誘致し、以来、チッソの企業城下町として栄えてきた。1955年には、水俣市の市税のうち50%をチッソが支え、水俣市の第2次産業従事者の8割をチッソの社員が占めていた。
チッソはアセトアルデヒド製造のために使っていた有機メチル水銀を含んだ排水を海にそのまま垂れ流していた。1950年代から、水俣市の沿岸部で「狂い死に」する猫が発見されるようになった。徐々に、水俣湾を漁場に漁で生計を立てていた漁民や、魚介類を食べてきたその家族、近隣住民たちが、発病した。手足がしびれ、視野が狭くなり、後に視力を失い、倦怠感を覚え疲れやすくなり、手足が曲がり、突如痙攣を引き起こしてのたうち回り、犬のような奇声を発して、酷い苦痛のうちに亡くなっていく。水俣病の公式確認は1956年5月1日だが、原因究明が何年も進まず、その間もチッソは有機水銀を海に流し続け、被害は不知火海沿岸地域の広範囲に拡大していった。
その間、患者や、地域が受けた打撃は計り知れない。豊穣の海が破壊された。水俣病患者は決して治ることのない病気で苦しみ続ける。患者への差別、偏見。認定患者とそうでない被害者間での補償額の差異が不公平感や妬みを生み、水俣地域の農作物が売れないといった風評被害や、水俣市出身者が自分の出自を名乗ることができない……等々。「水俣病はいまだに被害の全容が分かっていない。60年経ってもなお終わっていない」と、水俣市福祉環境部環境モデル都市推進課の大崎伸也さんは話す。
国が公式に「水俣病の原因はチッソの工場排水に含まれるメチル水銀である」と発表し、公害病と認め補償を開始したのは1968年になってからだ。1990年に水俣湾のヘドロの掻き出しと埋め立てが終わり、1996年には水俣湾の有機水銀の数値が4年連続で基準値を下回ったことから、「安全宣言」が出され、漁場の柵が取り払われた。少しずつ、漁が始まっていった。何十年にもわたり、人も、人間関係も、ズタズタに傷つき、引き裂かれたコミュニティを、もう一度結び直そうーー。船と船を結ぶ「もやい」を、もういちど結び直すという意味を込めて、「もやい直し」が始まった。「対話と恊働による町づくり」を掲げ、市民挙げての町づくりの新しい旗印になったのが「環境」だ。
水俣病を経験してきた、その歴史をプラスに転じて「環境と循環の町づくり」をしていこう―–。水俣市は1992年に「環境モデル都市宣言」をおこなった。

水俣市福祉環境部環境モデル都市推進課の大崎伸也さん。「子どもに誇れる故郷を残したい」
■水、ごみ、食べ物に気をつける。
市民が主体となって環境の町づくりをしていくには、具体的かつ行動に移しやすいキャッチフレーズが必要だ。水俣病は、「ゴミ」(有機水銀)を「水」(海)に流し、魚を通して「食」べたことで起こった。だから、水俣市では「水とごみと食べ物に気をつける」、すなわちそれは生命(いのち)を大切にすることである、を合い言葉に、数々の施策を打ち出していった。
水俣市はたいへん水の豊富な地域である。水俣市の絵地図に、自分の地域で飲み使っている水がどこから来て、どこに行くのかを調べる「水のゆくえを知る」プログラムをつくり、市民や子ども向けに啓発をおこなった。排水の質に気をつけるべく合成洗剤からせっけんへの切り替えを推奨した。
また、「安全・安心」を打ち出す有機農業・環境配慮型農業を積極的に推進していった。こうした農産物や伝統的なものづくりに取り組む人たちを、環境マイスターとして認定する制度や、地域の環境を住民自らの手で守っていくための協定づくり「地区環境協定」、そして「村丸ごと生活博物館」の認定で、環境配慮のライフスタイルを観光資源として内外に発信する動きが生まれた。
特筆すべきはゴミの高度分別で、「捨てればゴミ、分ければ資源」と呼びかけ、家庭ゴミの24種類の高度分別に取り組んだ。燃えるゴミと生ゴミは週2回、それ以外は月に1回地域のゴミステーションで分別を市民自らがおこなう。この作業は老若男女の世代を超えたコミュニケーションづくりにも一躍買っている。資源の売却益は年間1000万円を超え、そのお金は全額地域に還元するのも水俣市の特徴だ。
水俣市では、水源にあたる山間地域に産業廃棄物の最終処分場の計画が立ち上がった2003年から、2008年に事業者が撤退を決定するまで、市民が一丸となって反対運動を展開した。「産廃の最終処理場を反対するからには、自分たちのゴミにも責任を持つ。市の焼却場が2026年を目処に寿命になると言われているが、それまでにゴミを出さない仕組みをつくってゆく」と大崎さん。それが2009年11月の「ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言」につながり、2026年までに、焼却や埋め立てによるゴミ処理に頼らないまちづくりを模索していく。かなり難度の高い目標だが、環境ISO14001を自治体として取得し、その手法を学校や店、事業所、家庭に落とし込み、PDCAサイクルで進捗を確認していく手法を地域全体で共有しているため、目標遂行型での実践が望める。
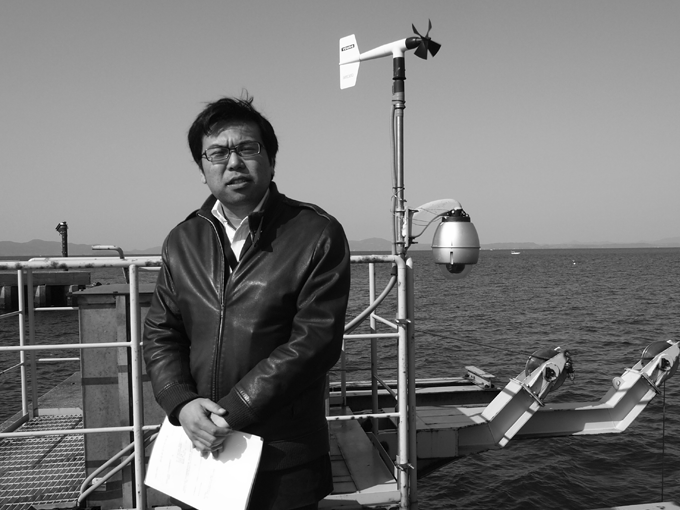
波力発電の前で。建設技術研究所の種浦圭輔さんは、水俣の漁師さんたちに惚れ込んでいる
水俣湾の埋め立て地には、リサイクル・リユース関連の環境ビジネスに取り組む企業を誘致し、2001年に「エコタウン」として始動した。その中心的な役割を担っているのがリユースびんを扱う田中商店専務の田中利和さんだ。
リユースびんの事業は、焼酎などの一升びんやビールびん、生協で使うジャムや調味料のびんなどを、一度きりの使用で破砕してリサイクルに回すのではなく、繰り返し洗って使うことでゴミを減らしCO2も削減する。田中さん自身はものすごいアイデアマンで、「毎月一つはビジネスが増えていく」と、地域を巻き込んで次々に新しい事業を展開していく。工場の中にリユースびんを加工し生活雑貨やガラス工芸品をつくる「リグラス工房」を設けたり、南九州の焼酎メーカーと共同で使う900ml統一リユースびんの事業を開始、障がい者の雇用や工場見学のエコツアー受け入れ、地元の工業高校に依頼して開発した洗びん機の導入などをこれまでにおこなってきた。「楽しくないと、人はついてこない。環境で水俣市全体を元気にしたいきたい」と話す田中さんは、水俣の事業者代表として、市民を引っ張っていくリーダー格でもある。
2008年には政府が提唱した環境モデル都市に選ばれ、2011年には日本初となる「日本の環境首都」になった水俣市。「水俣市民の環境意識はかなり高い。行政の役割は、市民の皆さんのアイデアやこうしたいというまちづくりのビジョンを形にしていくこと」と大崎さんは言う。

リユース業界の有名人、田中商店の田中利和さんは、数々のユニークなアイデアで業績を着実に伸ばしている
■ 100%再生可能エネルギーの水俣市を目指す。
「水俣市で使うエネルギーは、100%再生可能エネルギーでまかなうビジョンを掲げている」
こう話すのは、水俣市産業建設部総合経済対策課の草野徹也さん。水俣市は水量が豊富で、またJNCが自家発電用に建造した流下式の水力発電で、売電量にして市内のエネルギーの3割をまかなうことができるほどの再生可能資源量があるという。
今年度は埋め立て地のエコタウンを含めた産業団地全体で、「ゼロカーボン産業団地プロジェクト」に取り組む。水俣湾の残さで埋め立てた地域は大規模構造物の建設が難しく、それは逆にメガソーラーを設置の適地とも言える。市民出資などでPPS(特定規模電気事業者)を立ち上げ、豊富な水量を生かした小水力発電、メガソーラー、バイオマス発電や熱供給を組み合わせて、まずは産業団地からのゼロカーボンを目指していくという。
「エコタウンには、リユースびんや家電製品のリサイクル業者、アスファルト再生などの静脈産業がある。ここから新しいものづくりを提案し、付加価値を高めて新たな”水俣ブランド”を展開していきたい」と、草野さんは展望を語る。
丸島漁港では、すでに地域向けスマートグリッド実証実験が始まっている。国内では初となるつるべ式の波力発電(定格1kW)の耐久試験と、太陽光発電(定格3.36kW)、エネファーム(定格0.75kWの家庭用燃料電池)、蓄電池(容量12kWh)を組み合わせ、電力供給ネットワークを構築している。エネファームの副産物である温水は、漁師のシャワーとして活用している。現在はサーバー設置場所の照明に電気を利用しているが、今後は海藻の養殖用水槽のポンプの電源に利用する。
スマートグリッドの実証実験を担当する建設技術研究所の種浦圭輔さんは、「海藻の養殖のエネルギー源として、太陽光や波力などの再生可能エネルギーを利用すれば、環境付加価値が高まり、第6次産業として水俣ブランドを売り出すことができる。漁協の人たちは常に未来に向けて希望を掲げている」と、水俣の人の先見性や風土に惚れ込んでいる様子だ。
水俣市福祉環境部環境モデル都市推進課の岩下一弘さんは、「先端の研究者や技術者に地域を実証フィールドとして提供し、ネットワークとつながりながら、いかに新しい価値を社会に提案できるか。ここに、今後の地方の生き残りがかかっているかもしれない」と話す。
“低炭素”を切り口に、技術のみに走っていく日本の風潮に警鐘を鳴らすのは、水俣病資料館館長の坂本直充さん。「エネルギーを足下からどうつくっていくのか。水俣病の経験がある水俣市だからこそ、命の価値に重きをおいた生活文化としての展開と、価値の創造が可能になるだろう」と、語る。
「私は、水俣が大好きです。そして、自分の子どもたちに、自分の生まれた土地を誇りに思ってほしい」
3人のお子さんがいる大崎さんの願い。かつて汚染され苦しんだ「ミナマタ」は、環境首都として新しい輝きを放ち、世界の「ミナマタ」として再び脚光を浴びている。ふるさと「ミナマタ」は、未来の子どもたちの誇りになるに違いない。

水俣病資料館の坂本直充さん。「生命」を中心とした新しい価値創造を、と訴える
生活マガジン
「森ノオト」
月額500円の寄付で、
あなたのローカルライフが豊かになる
森のなかま募集中!




