
■仕事or休み、それが人生だと思っていた
東京にある小林久美さんのオフィス近くで待ち合わせをしたところ、やってきたのは、はつらつとしながらもやさしい笑顔が魅力的な女性。今回「森ノオトを支えるプロフェッショナルたち」というテーマで森ノオトの役員を取材させていただくことになり、久美さんの取材に手を挙げたものの、そのグローバルなご活躍を聞いてかなり緊張していた私の心をその笑顔でほぐしてくれました。

終始やわらかい雰囲気で進んだインタビューでは、地域のサッカーチームというローカルな話から気候変動といったグローバルな話まで多岐にわたりました。久美さんの語りを通して、全てのものごとが同一直線上につながっていることを学ばせていただきました
20代の頃は金融の世界で仕事にどっぷり浸かり、仕事以外は休む時間、という生き方をしていたという久美さん。仕事の実績を積み上げていくことがキャリアになり、そうやって歳を重ねていくのが人生だと思っていたそうです。
そこに転機が訪れたのは30代で産休・育休を取った時だったとか。仕事を離れて生活する中で、世の中には「仕事ではない部分」がたくさんあると気づいたのだそう。子育てで手が足りない時に友人や地域の方に助けられるような経験をするなかで、仕事以外のところで地域の暮らしが成り立っていると実感し、自分もそういった部分にも時間を割けるようになりたいと思うようになりました。
仕事と子育てと地域のことを同時にやっていくことは当時の働き方では難しいと感じ、公認会計士の資格を持っていた久美さんは、フルタイムの会社をやめ、独立するという決断をしました。そうすることで「自分のリソースをどこに配分していくか、主体的に自分の時間を編集できるようになった」と話します。
独立後は仕事のペースをおさえ、実家の事業再生や、暮らしている地域のコミュニティ活動に携わるなど、自分がやりたかったことを少しずつ展開していきます。
そんな中、2016年に訪れたポートランドで森ノオト理事長の北原まどかと出会い、目指す地域社会像を共有するローカル目線で意気投合したのが森ノオトに関わるきっかけでした。

サスティナブルな都市のパイオニア的存在であるポートランドで久美さんと森ノオトが出会ったのは必然だったのではと感じさせるほど、インタビュー中、2人の目線に近いものを感じました(写真:森ノオト2016年の記事より)
■スポーツの世界をサスティナブルに
2017年には、スタートアップ、スポーツチームやアスリートのサポートを行うTokyo Athletes Officeを設立し、現在はJリーグ監事のほか、アスリートのセカンドキャリア支援を行う会社の取締役を務めるなど、スポーツに関わりの深いお仕事を数多くされている久美さん。
スポーツに関わることになったきっかけを伺ったところ、子どもの頃に大家族で暮らすなか、スポーツのルールなどを教えてくれる伯父の存在も身近にあり、家で友人たちと集まってスポーツ観戦を楽しんできだ原体験があったそうです。
スポーツの魅力を実体験として感じてきて、「人を元気にしてくれるスポーツが、社会の中にしっかり存在し続けてほしい」と願うと同時に、スポーツの世界は関係者が総じて無理をし、120%の力を発揮してストレッチしながらどうにか運営しているという現実に危機感を覚えます。無理してやっているものは続かない、それはサスティナブルではない。そんな思いに加え、金融の世界で生きてきた久美さんから見ると、スポーツチームの運営で、金融や資金調達、仕組み(ガバナンス)について支える存在が少ないと感じ、そこに自分が関わっていこうと決意しました。
アスリートのセカンドキャリア支援等の実績を重ねるなかで、現在はJリーグや日本陸上連盟などのスポーツ団体でも監事という重責を担っている久美さん。これまで行ってきた具体的な活動を尋ねると、二つの事例を教えてくれました。
「何のためにやっているのか?」をみんながわかる形の理念として示す
一つめは、愛媛県今治市を拠点にするプロサッカークラブ、FC今治のホームスタジアムである「今治里山スタジアム(現:アシックス里山スタジアム)」を作る際の資金調達支援。スタジアム設立には40億円を集める必要がありましたが、ここで久美さんがまず取り組んだのは「このスタジアムを作って何をしたいのか?」という点を関係者の間でしっかりと議論して掘り下げていき、半年くらいかけてチームでビジョンをしっかりと共有するための伴走支援すること。「資金調達の形をつくることと、しっかり語れる理念を関わるみんながわかる形にすることは、どちらも同じぐらい大切なんです。まずはそこに時間をかけて取り組みました」と話してくださいました。その結果、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」というビジョンに共感する方からの支援が集まり、目標額の達成に至りました。

「文化・交流拠点として地域と人を繋ぐ。365日賑わうスタジアム。」をコンセプトに掲げているアシックス里山スタジアム。このスタジアムでは、サッカースタジアムとしての機能だけではなく、スタジアムを核に、新しい共助のコミュニティの実現を目指しています。「里山スタジアムは、コンクリートの壁に区切られず地域の里山と一体になっていて、里山の向こうに海が見える、というのが好きなポイントです」と久美さんは話します(写真提供:小林久美さん)
巻き込まれ方をデザインし、関わりしろを増やす
もう一つは、久美さんのお子さんが参加している地域のサッカーチームの保護者代表を経験するなかで、情報共有のしくみを構築したこと。BAND(バンド)という無料アプリを使い、紙をほぼ使わず保護者間の連絡調整や情報共有ができるようになりました。
中でもお気に入りの仕組みは、アプリの中のオープンチャット。近所のサッカーができる公園に子どもたちが遊びに行く際、「今から行く」「誰々が遊んでいた」などのやりとりを気軽に行えるようにしました。その公園に行ったら誰かが遊んでいて、誰かが見守っているという環境を、ツールの力を借りて作り出すことができました。
地域のスポーツチームは保護者による任意団体が運営することが多いですが、保護者に関わりたい気持ちはあっても、仕事内容や関わりしろが見えにくいこともあり、負担感を覚えやすい状況があります。ツールを実装したことで情報共有のプロセスが明確化されて、仲間に浸透していくことで関わり方が変わり、結果的に活動の負担感も変わるため、「巻き込まれ方をデザインすることの大切さを感じた」と久美さんはいいます。
この「巻き込まれ方が変わると関わる負担感も変わる」という気づきは、子どものサッカーチームの話にとどまらず、Jリーグのサポートなどさまざまな場面で今に生かされているそうです。

取材中、実際のアプリを見せていただきました。保護者はとても忙しいため、いかに負担をかけずに生活動線の中で情報にふれられるかという点にも気を使ったのだとか。情報の置き場所をリデザインし、ここだけは必ず見ればいいという仕組みを作り、シンプルな取扱説明書もご自身で作成されました
私たちは余白を生み出すということをもっと本気でやっていい
紹介いただいた二つの事例に共通するのは、伴走者には観察力と見通す力が求められるということ。
Jリーグのチームは現在全国に60ありますが、置かれている地域やステークホルダーとの関わり方はさまざまです。他地域の成功事例をそのまま持ってきてもうまくはいかず、置かれている現状やその地域をしっかり観察する存在が必要になります。
地域のスポーツチームは、その地域ごとに独自の生態系があり、その関係性を一つひとつ丁寧につないでいくことが必要になります。いわゆる「ドブ板」ともいう、地域との顔つなぎはとても手間と時間がかかることで、目に見えた効果をすぐに実感できるものではありません。「それらの細い糸を丁寧につないでいくことでできるコミュニティとしての価値が重要で、一部分のみを切り取って営業効率やコストパフォーマンスを求めてしまうとうまくいきません。そのプロセスにこそ意味があり、地道に地域を回って大事な思いの重なりをつなぎ合わせていくことに時間を割けるよう、それ以外の部分での効率化が必要になってきます」と久美さんは力説します。
大切なことのために時間をつくるーー。その「余白」をつくるのに久美さんが期待しているのが、AIやDXです。ルーティン(日常業務)を小さくして、新しい何かを作ってみたり、工夫したりすることに時間を割くため、今ある週5の仕事を週3でできるように効率化し、余白時間をクリエイティブな活動に使えるような社会になってほしいと久美さんは話します。

久美さんが関わったアシックス里山スタジアムでは里山スタジアムの側面に畑を作る活動などもしたそうです(写真提供:小林久美さん)
Jリーグでは2025年、未来の子どもたちが安全にスポーツを楽しむことのできる地球環境を目指して、気候変動への具体的なアクションを数値化して発信するスポーツポジティブリーグにアジアで初めて参画しました。プロスポーツの持つ発信力によって、私たち市民が社会的な課題を知り、アクションをするためのひと押しになるのです。
「あるJリーグのチームは、選⼿⾃⾝が地域に積極的につながる活動を始めたことで、地域に愛されるチームとして大きく成長しました。選⼿に最も⼤切なのは集中してプレーすることなので、その妨げになるようなことはさせられない、という考えが主流のなかで、それを打ち破って⾃ら積極的に地域につながろうとした選⼿たちは素晴らしいと思います。プロスポーツチームは1回の試合で何千、何万という⼈に発信できる⼒があります。チームが地域との関わりしろをどうつくるか、愛される組織になるためのガバナンスづくりを⽀えていきたいです」と、冷静かつ愛情深い伴走者の表情を見せてくださいました。
■森ノオトのようなプラットフォームがいろんな地域にあるといい
最後に、久美さんに森ノオトのどの部分に期待してくださっているのかを聞いてみました。
言葉で表現するのに悩みながらも、「地域に根付いている人たちが、誰もがメディアになれる可能性を持っている」点に加えて、「自分で自分たちの住む地域社会を作っていくために、自分の時間とリソースと能力を使って活動している人が地域にたくさんいても、森ノオトのようにそれをつなぐメディアがないと形にならない。形にしてくれる存在がいて、それが長く続いているということ自体に励まされる」と答えてくださいました。
週5の仕事が効率化によって週3になり、できた余白をスポーツやクリエイティブな活動、社会活動にあてていく際、森ノオトのようなプラットフォームがあれば活動が増幅していくと感じているそうです。
「社会活動の時間は、自分にとってのセーフティネットでもある」と久美さんは語ります。企業で働く人にとって、企業以外のところでの自分の居場所をつくるというのは一朝一夕でできるわけではありません。しかし、一企業だけで働くスタイルが持続可能でなくなっている現代において、労働と社会活動の比率が変わっていく未来が予想されます。久美さんは、仕事と社会活動、その両方に片足ずつ置いておきたいと考えているそうです。
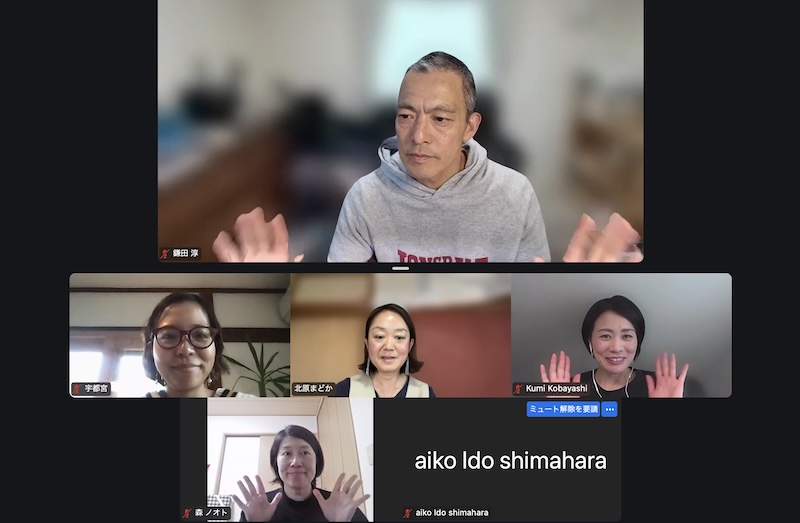
森ノオトの理事会では常に活発な議論で盛り上がる。「大きな視点でビジネスの動向と地域の現場をつないでくださる久美さんの存在に励まされている」と北原理事長
フルタイムで働きながら森ノオトライターとして活動している私にとって、今回の取材は首がもげそうなほどうなずきたくなるお話がたくさんありました。今は余白がほとんどない中に無理やりライター活動をねじ込んでいる感覚があり、「無理してやっていることは長く続かない」という言葉にハッとさせられたりもしました。
そんな状態でも私が森ノオトに関わろうとしているのは、私自身も、職場でもない、家庭でもない、サードプレイスのようなところとつながっていたいという思いがあるからです。加えて、活動時間の確保という意味での余白以上に、人の気持ちの部分に余白がほしいと感じていることに気がつきました。余白のない社会は相手に寛容になれない社会だと思います。
業務の効率化について話をするなかで出た「ツールの導入には最初はハードルがあるけれど、そこに労力とリソースを割いて日常業務に導入していかないと変化は起こらない」という言葉にも強く共感し、自分が働く上で強烈に意識していきたいです。
そして、森ノオトとしては、自分らしく地域に関わりたいと思っている団体や個人に対して、いかに関わりしろを作っていくかをこれまで以上にしっかり考えていかなければならないと感じました。「森ノオトのようなプラットフォームがいろんな地域にあるといい」。久美さんからいただいた森ノオトへの温かいエールの言葉を胸に、誰もが軽やかに地域参加ができる場と機会を提供することができる団体として、今後も地域に必要とされ続ける森ノオトでありたいです。
生活マガジン
「森ノオト」
月額500円の寄付で、
あなたのローカルライフが豊かになる
森のなかま募集中!





