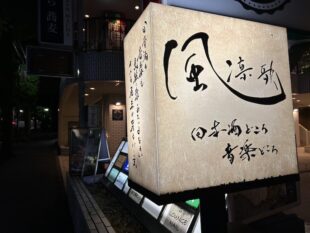今年は暖冬だといわれていました。
東京での初霜が観測されたのは今年に入ってから、1月8日。これは平年より3週間近く遅いのだとか。
急に冷え込んだその日の朝、私は子どもの幼稚園へ向かう道のりで、前日までとはまったく景色が変わったことに驚きました。そして、その美しさは息をのむほどでした。
緑の雑草や、秋に地面に降りおりた銀杏や柿の葉などが、うっすら白化粧していました。
まるでフエルト細工のようで、さわったら固く冷たいであろうそのギャップがまた面白く感じました。

霜が降りた様子。雪でもなく、凍っているわけでもなく、繊細でとても美しかった

七十二候では10月23日が霜始降(しもはじめてふる)。霜が降りた、というのも季節の移り変わりを知る、自然からの大切なお便り

雪の上でみつけたヤマノイモ。豆科の植物
白の世界にある「ほんの少しの色」って、とても映えますね。
色の濃淡の幅は広くはありませんが、繊細な色の変化を味わえるのが冬ならではの楽しみだなぁと感じます。
「白」という色ひとつとっても、伝統色では様々な捉え方があるようで、少し調べてみました。(参照:『美しい日本の伝統色』山川出版社、『暮らしの中にある日本の伝統色』大和書房)
・胡粉(ごふん):貝殻を原料にした顔料。貝殻をすりつぶしたような白色。
・灰白色(かいはくしょく):少し灰色を含んだような白。
・乳白色(にゅうはくしょく):ミルクのような少し黄が入った不透明な白植物に由来し色の名前がほとんどのなかで、動物由来の名称が入ったものは本当に珍しいようです。
・白練(しろねり):生絹の黄色みを消したあとの白い絹の色。真っ白。
いにしえの日本人のわずかな違いも捉える繊細な感覚にも感動するとともに、「白は白でなくてもいい」と違いに寛容で、それを楽しんでいるような気がして、現代に通じる新鮮な感覚かなと思います。

新豆が出て、お味噌を仕込む時期でもありますね。豆もこんなに種類豊富、色彩豊かです。“豆”に由来する色と言えば小豆色

うっすらと灰色の景色も美しい
日本ではその昔、「枯れ野狩り」というのを楽しむ風習もあったようです。
春の花見のように、冬で草木が枯れた様子を見て楽しむのです。
近頃では見た目の華やかさにのみ魅力をおきがちですが、季節が巡る過程での控えめな、地味な部分をも味わってしまう、この感覚。
春の息吹を爆発させるための充電期間とも言えるこの季節を大切に、前向きに捉えて向き合っていた心意気には、ハッとさせられました。
冬の自然の姿は、インパクトある色が少ないからこそ、自分の気持ちによって感じることがそれぞれにあるのかも。
ふと立ち止まって春からのことを想像し、新年度にむけて気持ちの準備をするのにちょうどいいのかもしれませんね。
確実に近づいている春に向かって、私たちも頑張りましょう!
生活マガジン
「森ノオト」
月額500円の寄付で、
あなたのローカルライフが豊かになる
森のなかま募集中!